
行政書士
宮城 彩奈
「許認可申請や経審」から「建設業法務」「補助金を活用した資金調達」まで、建設業者様の経営全般をサポート。
また、許可取得後についても「請負契約書のリーガルチェックや作成」から「許可や資格者の期限管理」「建設業法違反にならない技術者の配置」まで継続的に経営サポートをしている。
contents
[建設業法]
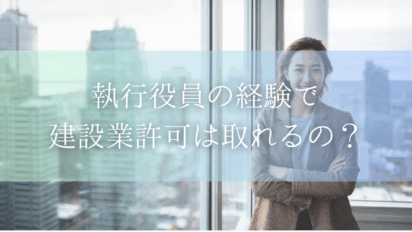
建設業許可の取得に必要な「経営業務管理責任者」の要件は、2020年の建設業法改正により大きく緩和されました。これまでのように、取締役や代表者としての経験以外に、執行役員としての経験が5年以上ある方や、経営業務管理責任者を補佐してきた経験が6年以上ある方でも、許可取得が可能となっています。
しかし、制度が緩和された一方で、その実態を証明する書類の重要性は以前にも増して高まっています。特に補佐経験者としての申請では、稟議書や組織図、業務規程など、実務での役割を示す資料を年単位で準備する必要があります。
この記事では、「執行役員経験」や「補佐経験」をもとに建設業許可を取得するためのポイントを、制度の背景から書類収集の注意点まで、実務に即してわかりやすく解説します。
目次

建設業許可を取得するためには、いくつかの法定要件を満たす必要がありますが、その中でも特に重要とされるのが「経営業務管理責任者の設置」です。これは、許可を受ける建設業者の営業所において、経営に関する実務的な責任を持つ人物を置くという制度であり、事業の継続性や健全性を確保するための基盤と位置付けられています。
かつては、「経営業務管理責任者」本人が、建設業に関する経営経験(たとえば5年以上の個人事業主や取締役などの経験)を持っていることが原則要件とされており、特に中小企業や事業承継を考える企業にとっては、後任選定のハードルが高い制度でした。
しかし、2020年(令和2年)の建設業法改正により、制度の柔軟化が図られました。改正後は、従来型の“経営業務管理責任者”という立場そのものの要件ではなく、「経営業務の管理責任を適切に遂行できる体制が整っていること」が重視されるようになったのです。
この流れの中で、新たに認められたのが「執行役員としての経験」や「経営業務管理責任者を補佐していた経験」を根拠に申請できる仕組みです。これにより、登記上の代表者や取締役でなくとも、実質的に経営に携わっていた人物が、建設業許可取得における要件を満たせる可能性が広がりました。
この制度の変更は、特に世代交代や組織変更を予定している建設業者にとって、大きな転換点となっています。
建設業許可における経営業務管理責任者の要件は、2020年の法改正を機に緩和され、執行役員としての経験も5年以上あれば認められる可能性があることが、明文化されました。これは、従来の「取締役以上」という硬直的な要件を見直し、実質的な経営参画を重視する方向に制度が変化したことを意味します。
しかし、この執行役員の経験がすべて認められるわけではありません。重要な前提条件として、「取締役会を設置している会社」であることが求められます。
この要件が課されている理由は、執行役員という役職が法律上の役員ではないためです。執行役員はあくまで社内的な呼称であり、その職務内容や権限は企業によって大きく異なります。そこで制度上は、一定の統治体制が整っている取締役会設置会社において、執行役員が実質的な経営業務に関与していたことを重視しているのです。
反対に、取締役会を設置していない会社、つまり取締役1人または少人数で経営を行っているような中小企業では、たとえ「執行役員」としての肩書きがあっても、それが正式な経営業務管理の経験と見なされない場合があります。この点を見落としたまま申請を進めると、書類審査で差し戻されるケースが実際に発生しています。
加えて、執行役員としての経験を申告する際には、ただ肩書きがあったというだけでなく、実際にどのような業務を担当し、どのような経営判断を行っていたかを示す具体的な証拠が求められます。たとえば、取締役会議事録への登場、稟議書への承認履歴、契約締結権限の付与記録などです。
このように、執行役員という立場を許可取得の根拠とするには、企業体制と役職内容が制度の要件に適合しているかを慎重に確認する必要があります。単なる名ばかり役職では通らない点に十分注意しましょう。
建設業許可における経営業務管理責任者の要件緩和により、執行役員経験だけでなく、「経営業務管理責任者を補佐していた経験が6年以上ある者」も、経営業務の管理体制要件を満たす人物として認められるようになりました。
この「補佐経験6年」の制度は、取締役などの役職に就いていなくても、実質的に経営業務の管理を補助していた人物に対しても、建設業許可の経営体制構築が認められる道を開いたものです。
執行役員経験は「取締役会設置会社での役職経験」という組織上の地位が前提となるのに対し、補佐経験はあくまで職務内容や役割の実態が問われます。社内での肩書きが課長や部長であっても、実際に経営業務の補助を継続的に行っていれば要件を満たす可能性があります。
「経営業務管理責任者の補佐として6年以上の経験があること」を証明するためには、原則として5つの確認事項に対応する資料を提出する必要があります。
なお、1つの資料が複数の確認項目を兼ねている場合は、その分の提出を省略することが認められています。以下に各項目と該当資料をまとめます。
① 地位に関する証明
② 補佐の根拠を示す内部規程類
③ 補佐業務の実績を示す書類(毎年1件以上が原則)
④ 直属の役員との継続的な関係を示す書類
⑤ 法人に常勤していたことを示す証明書
これらの資料は、単に在籍していたことを示すだけでなく、どのような立場で、どんな業務に、どの程度関与していたのかを客観的に裏付けるものです。中でも稟議書などは、本人の氏名・役職・決裁権限の有無などが確認できる内容である必要があります。
また、都道府県によっては求める資料の粒度や評価基準に差があるため、提出前に所轄の窓口へ確認することが重要です。審査が厳しく、補佐経験が認められないケースもあるため、必要に応じて行政書士などの専門家と連携しながら準備を進めると安心です。

建設業許可の取得には、経営業務管理責任者(またはその補佐経験者など)だけでなく、その他にも複数の要件を満たす必要があります。ここでは、許可取得までの一般的な流れと、注意しておくべきポイントを時系列に沿って解説します。
まずは、建設業許可の取得に必要な主な3要件を確認します。
とくに、経営業務管理責任者の要件を「執行役員経験」や「補佐経験」で満たす場合は、候補者の職歴や書類整備の見通しを早めに立てることが不可欠です。補佐経験の場合は6年以上の実績と各種証明書類が求められるため、時間に余裕をもって準備を始めましょう。
次に、必要となる書類の一覧を整理し、収集を始めます。個人事業主か法人か、そして新規か更新かによっても若干の違いがありますが、主なものとしては以下の通りです。
各都道府県で様式が異なる場合があるため、必ず申請先の自治体サイトか窓口で最新版を確認してください。
書類が整ったら、建設業許可申請書一式を作成します。記載ミスや不備があると受理されないこともあるため、事前審査(事前相談)を受けることが推奨されます。
申請は、法人の本店所在地を管轄する都道府県庁(または出先機関)に対して行います。郵送不可の場合もあるので、提出方法の確認も忘れずに。
書類審査後、おおむね30~45日程度で許可の可否が通知されます。無事に許可が下りると、「建設業許可通知書」が交付され、晴れて正規の建設業者として営業を行うことができるようになります。
なお、許可は業種ごとに分かれており、「一式工事」と「専門工事」で区分されています。また、許可の種類(知事許可・大臣許可)や一般・特定の別も、請け負う工事の内容に応じて検討が必要です。

建設業許可の申請では、単に必要書類を集めるだけでなく、「いかに分かりやすく整理し、行政側が確認しやすい形で提出できるか」が審査通過の鍵となります。特に執行役員経験や補佐経験に基づく申請の場合、収集資料の内容が結果を大きく左右します。
都道府県によって様式や細部の記載要件が異なるため、提出先の自治体ホームページで必ず最新版を確認しましょう。
これらの立場で申請する場合、上記の基本書類に加えて、次のような資料の準備が重要になります。
特に補佐経験の場合は、「業務を補佐していたことの実態がわかる資料」をいかに積み上げられるかが最大のポイントです。会社としての一貫した姿勢と、客観的な裏付けを意識して書類を作成しましょう。
建設業許可の取得において、「経営業務管理責任者」の設置は避けて通れない要件の一つです。かつては取締役や代表者としての経験が必要でしたが、法改正により、執行役員としての5年以上の実務経験や、経営業務管理責任者を補佐していた6年以上の経験でも、要件を満たせるようになりました。
ただし、これらの制度は一見ハードルが下がったように見えて、実際には「証明書類の整備」が非常に重要なポイントになります。とくに補佐経験の場合は、毎年1件以上の稟議書類など、細かな実績の積み重ねが求められるため、申請準備には十分な時間とリソースが必要です。
許可取得に向けては、まず自社の体制を棚卸しし、該当しうる人物がいるかどうかを精査するところから始めましょう。そのうえで、組織図や規程、社内文書、公的証明資料などを集め、行政庁の窓口と相談しながら申請準備を進めていくことが成功の鍵となります。
今回の法改正によって、承継や組織再編を予定する建設業者にも柔軟な対応が可能になりました。条件を正確に理解し、制度を正しく活用すれば、自社の未来を見据えた体制整備にもつながります。「人材の経営力」こそが、これからの建設業における競争力そのものだという意識を持つことが、申請の一歩目となるでしょう。

執行役員の経験があれば、建設業許可の経営業務管理責任者になれますか?
はい、なれます。ただし要件があります。取締役会設置会社において執行役員として5年以上の実務経験があり、かつその業務内容が経営に関する意思決定や管理業務を伴っていたことが証明できる必要があります。単なる役職名だけでは不十分なので、稟議書や職務分掌の資料を整えることが重要です。
補佐経験6年の「補佐」とは具体的にどんな業務ですか?
経営業務管理責任者の指示のもと、経営判断に関与するような業務を補助していた経験が該当します。たとえば、工事受注に関する稟議への関与、予算管理、契約締結の準備、部門責任者としての業務執行などです。「補佐していた事実」を客観的に証明する資料が必要となります。
経営業務管理責任者の要件はどう変わったのですか?
2020年の建設業法改正により、「経営業務管理責任者本人の経験」だけでなく、「執行役員経験」や「補佐経験」でも体制として認められるようになりました。これにより、承継や人材不足の現場でも柔軟に対応しやすくなりましたが、その分、書類による実態証明の重要性が増しています。
建設業許可の申請で必要な書類はどこで確認できますか?
各都道府県の建設業許可窓口、または自治体の公式ホームページで最新の様式やチェックリストが確認できます。申請書以外にも、組織図、登記簿謄本、稟議書、保険記録など、多くの補足書類が必要になります。建設業許可申請には行政書士に依頼するのが安心です。
補佐経験や執行役員経験があるが、書類が足りない場合はどうすればいいですか?
その場合はまず、行政庁の相談窓口や行政書士に相談し、不足資料をどのように補完できるかを検討しましょう。場合によっては証明書の作成や、過去の書類の再発行、上司や代表者の証明書で補完することも可能です。証明力の高い資料を複数組み合わせることがポイントです。

建設業許可は、取得するためには、経営業務の管理責任者・営業所技術者・財産的基礎という3つの厳しい要件をすべて満たす必要があります。
「建設業許可の申請が難しくて分からない…」
「執行役員の経験は使えるかな…」
「財産的基礎が満たせているのか分からない…」
建設業許可の取得は、企業のステップアップの大きなチャンスです。
そんな方は、まずは専門家に相談するのがおすすめです!
サポートを受けることで、スムーズな申請・時間をロスすることなく許可を取得することができます。
📩 建設業・不動産業専門のあやなみ行政書士事務所へのお問い合わせはこちらから!
contact
あやなみ行政書士事務所への相談・お問合せは、以下の方法でご連絡ください。
*お問い合わせ内容により、有料相談になる場合がございます。(目安:5,500円税込/30分またはメール2往復程度)
*匿名及び非通知でのお問い合わせはご対応致しかねます。あらかじめご了承ください。
対応地域
神奈川県を中心とした首都圏に対応。
神奈川県:横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・保土ケ谷区・磯子区・金沢区・港北区・戸塚区・港南区・旭区・緑区・瀬谷区・栄区・泉区・青葉区・都筑区)|川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区)|相模原市(緑区・中央区・南区)|横須賀市|平塚市|鎌倉市|藤沢市|茅ヶ崎市|逗子市|三浦市|秦野市|厚木市|大和市|伊勢原市|海老名市|座間市|綾瀬市|葉山町
東京都:千代田区|中央区|港区|新宿区|文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区
千葉県:千葉市