
行政書士
宮城 彩奈
「許認可申請や経審」から「建設業法務」「補助金を活用した資金調達」まで、建設業者様の経営全般をサポート。
また、許可取得後についても「請負契約書のリーガルチェックや作成」から「許可や資格者の期限管理」「建設業法違反にならない技術者の配置」まで継続的に経営サポートをしている。
contents
[建設業法]
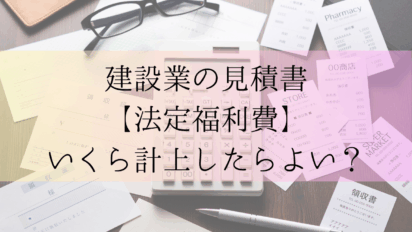
工事見積もりを作成する際、法定福利費(労災保険、健康保険、厚生年金、雇用保険など)は必ず含めなければなりません。しかし、どう計算してどのように標準見積書に落とし込むかで迷う経営者・経理担当も多いでしょう。本記事では、法定福利費の内訳と計算方法、標準見積書の書き方、発注側と受注側それぞれの注意点を、実例を交えて分かりやすく解説します。
目次

かつての建設業界では、社会保険に未加入のまま事業を継続している企業が少なくありませんでした。実際、以前は社会保険の加入状況が建設業許可の取得要件に含まれておらず、制度上も黙認されていた時代があったのです。そのため、法定福利費を見積書に明示するという意識は業界全体として乏しく、結果として公正な競争や労働環境の整備が阻害される状況が続いていました。
しかし、建設業界を取り巻く環境が大きく変化する中で、社会保険未加入問題が顕在化しました。低価格競争の中で、適正な保険料を負担せずに見積価格を下げる業者が存在する一方で、真面目に社会保険を負担している企業が不利になるという不均衡が生じていたのです。この構造的な問題は、技能者の処遇悪化や若年層の入職離れといった課題にもつながり、業界全体の持続性が問われるようになりました。
そうした流れを受け、国土交通省は社会保険未加入対策を強化。平成29年度以降、社会保険への加入が建設業許可の前提条件となり、現在では未加入のままでは許可そのものが取得できません。加えて、国交省は平成25年から「法定福利費の明示」を推進しており、見積書の中で法定福利費を明確に示すことが、受発注の透明性向上と建設業界の健全化に資すると位置づけています。
とくに、令和5年6月に更新された「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省)」では、見積書への記載方法まで具体的に示されており、実務レベルでの対応が求められるようになりました。つまり、法定福利費をただ負担するだけでなく、それを“見える化”することが、今の建設業経営において不可欠な取り組みになっているのです。
法定福利費とは、企業が従業員に対して法律上必ず負担しなければならない社会保険料のうち、「事業主が負担する部分」を指します。建設業の見積書においては、この法定福利費を正確に算出し、明示することが求められています。
代表的な法定福利費には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、そして労災保険の4つがあります。これらはすべて、労働者の生活を保障し、万が一の事態に備えるための社会制度です。ただし、各保険にはそれぞれ異なる役割と負担割合が設定されています。
たとえば、健康保険と厚生年金保険は、労使で保険料を折半するのが原則です。企業は従業員と同額を負担することになり、その分が法定福利費としてカウントされます。
雇用保険については、国が定める業種別料率に基づいて保険料が設定されています。建設業の場合は「建設の事業」という区分で料率が定められており、他業種よりもやや高めの設定となっています。見積を作成する際には、建設業専用の料率を用いる必要があるため、一般的な企業の料率と混同しないよう注意が必要です。
一方、労災保険は全額を事業主が負担する仕組みであり、そのため企業にとっては最も直接的な「法定福利費」となります。業務内容や業種により料率が細かく分かれているため、自社の業務実態に合致した区分で算定することが求められます。
このように、法定福利費とは単なる経費ではなく、従業員の安心と企業の信頼性を支える重要なコストです。公共事業の現場では、これらを適切に見積書に反映させることが、取引先からの信頼獲得にもつながります。

法定福利費を見積に正しく反映させるためには、各保険項目ごとの料率と負担区分を理解し、実際の給与額に応じて正確に算出する必要があります。ここでは、建設業における標準的な算出方法と、実務で使いやすい簡便な計算方法の両方を紹介します。
法定福利費は基本的に、従業員の給与額を基に次の4項目で構成されます。
たとえば、月給30万円(標準報酬月額:22等級)の従業員(40歳〜64歳、第2号被保険者)が1名いる場合、東京都・協会けんぽ加入・令和7年度の料率を用いて算出すると以下のようになります。
この場合、事業主が負担する法定福利費の合計は、50,850円となります。
なお、健康保険料のうち介護保険料(第2号被保険者分)は40歳〜64歳の加入者にのみ加算されるため、従業員の年齢構成によっても負担額は変わります。また、厚生年金保険は「標準報酬月額」によって算出されるため、日本年金機構が公表する等級表を必ず確認する必要があります。
実務では、細かな計算が難しい場面もあるため、国土交通省が示す「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」(PDF3ページ)にもあるように、「工事費に対して一定割合を掛ける」簡便な方法も認められています。
たとえば、労務費に対して15%〜17%を目安として算出するケースが一般的です。労務費が1,000万円であれば、150万円〜170万円を法定福利費として見込むという考え方になります。
ただし、この簡易算出法にも注意点があります。特に、介護保険料については、対象が40〜64歳の被保険者に限られるため、全体の保険料率を一律に掛けるのではなく、この年齢層の加入割合を考慮する必要があります。
国土交通省の資料では、協会けんぽ加入者全体における40〜64歳の構成比を用いて補正する方法が紹介されています。具体的には、次のような計算式が提示されています。
介護保険料率の算定式(事業主負担分)
= 協会けんぽの介護保険料率 × 1/2(事業主負担) × 加入率(40〜64歳の構成比)
このように、簡便法を使う場合でも、介護保険料に関しては40〜64歳の割合を想定した率の設定が推奨されているのです。協会けんぽのWebサイトでは、都道府県別の加入者年齢構成が公開されており、それを参考にすることで、より現実に即した算定が可能になります。
結果として、従業員の年齢構成や加入制度を踏まえた調整が、簡便法でも求められることを理解しておく必要があります。もちろん、公共工事や標準見積書を求められるケースでは、あくまで実数ベースでの正確な算出が基本です。

国土交通省が定める「法定福利費を内訳明示した見積書」は、社会保険等未加入問題の是正を目的として導入されたもので、特に公共工事では提出が強く推奨されています。
この標準見積書では、法定福利費を明細として明示することが求められ、元請・下請間での適正なコスト確保と、社会保険加入の徹底が目的とされています。
法定福利費を明示する際には、以下の保険項目の事業主負担分を、労務費から算出してそれぞれ明記します。
労災保険は制度上全額事業主負担であるものの、法定福利費とは別に扱われる場合があるため、記載の有無は企業判断によります。
| 工種 | 項目 | 数量 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 内装工事 | 労務費 | 一式 | 3,000,000円 | 作業員15名分 |
| 健康保険(事業主負担) | 一式 | 172,500円 | 該当労務費×5.75% | |
| 厚生年金保険(事業主負担) | 一式 | 274,500円 | 該当労務費×9.15% | |
| 雇用保険(事業主負担) | 一式 | 33,000円 | 該当労務費×1.1% |
健康保険や厚生年金には、「常時使用する労働者が5人未満の個人事業所」や「一人親方」など、加入義務のない適用除外者が存在します。これらの作業員については、法定福利費の対象外となるため、見積書上の法定福利費には含めないようにする必要があります。
つまり、労務費全体に料率を掛けるのではなく、適用除外者を除いた対象者に限定して算出することが求められます。実際には把握が難しい場合もあるため、元請・発注者と協議のうえ、適用除外の確認や内訳明示の要否をあらかじめ整理しておくと、トラブルの防止にもつながります。
元請けが内訳を確認した上で、最終的な支払金額を調整する仕組みも現場では運用されています。

法定福利費を標準見積書で明示する取り組みは、単なる帳票作成の形式にとどまらず、建設業界全体のコスト構造の健全化と、適正な労務環境の維持につながる重要な制度です。発注側と受注側のどちらか一方だけが対応していても意味がなく、双方が制度趣旨を理解し、正しい対応を行うことが不可欠です。
発注者は、見積書に記載された法定福利費を「交渉の余地がある価格要素」として扱うのではなく、必要な実費として尊重する姿勢が求められます。特に公共工事や大手元請企業では、国交省の制度趣旨に沿った対応がスタンダードとなっており、受注者が提示する法定福利費の内訳を否定せずに受け入れる体制づくりが求められます。
また、見積内容をチェックする際には、適用除外者の扱いや、料率・対象範囲が妥当かを確認する視点も重要です。不明点があれば、その場で減額交渉に進むのではなく、受注者に説明を求めるプロセスを丁寧に踏むことが信頼関係の構築にもつながります。
一方で、受注者には、法定福利費を正しく理解し、根拠をもって説明できる姿勢が求められます。単に「15%をかけました」といった大まかな説明ではなく、「労務費がこの金額で、東京都の健康保険料率が◯%、雇用保険は建設業の料率で1.1%です」といった具体的な裏付けがあれば、発注者からの信頼も得られやすくなります。
特に注意したいのが、過剰な上乗せです。法定福利費を見積書に明示することが定着しつつある中で、意図的に料率を高く設定したり、適用除外者を含めて算出したりすると、後々の減額交渉やトラブルにつながる可能性があります。必要な費用であるからこそ、根拠ある透明な説明が防衛線になります。
また、標準見積書の運用には、社内の経理担当や現場管理者との連携も重要です。料率や人員構成の情報を的確に反映させるためには、日頃から情報共有できる体制づくりも不可欠です。
建設業界における社会保険未加入問題への対策として、法定福利費を明示した標準見積書の作成が強く求められるようになりました。国土交通省のガイドラインを基に、健康保険・厚生年金・雇用保険といった事業主負担分の社会保険料を正確に見積に反映することは、もはや「任意対応」ではなく、業界標準の対応となりつつあります。
特に近年では、社会保険の加入が建設業許可の前提条件となり、法定福利費の明示が発注者からの信頼確保や競争力の維持に直結する重要なポイントとなっています。
算出にあたっては、各保険の最新料率や、標準報酬月額・年齢構成・適用除外者の有無など、細かな点まで丁寧に確認する必要があります。簡便な方法を用いる場合も、補正や根拠の明示を怠らない姿勢が、見積の説得力を大きく左右します。
そして何より重要なのは、発注者・受注者の双方が「適正な社会保険の負担は企業責任であり、健全な労務環境の基盤である」という共通認識を持つことです。形式的な書類作成ではなく、制度の本質を理解したうえでの運用が、今後の建設業の持続的な成長を支えていくでしょう。

法定福利費の見積はどの保険料が対象になりますか?
法定福利費の見積対象となるのは、健康保険(介護保険含む)、厚生年金保険、雇用保険の事業主負担分です。労災保険は法定福利費には含めないケースが多いですが、任意で内訳明示することも可能です。
標準見積書では法定福利費の内訳をどこまで書く必要がありますか?
国土交通省が定める標準見積書では、健康保険、厚生年金、雇用保険の事業主負担分を、個別に金額を算出して明示することが求められています。単に「法定福利費一式」と記載するのではなく、根拠を添えて提示することが望ましいとされています。
法定福利費の率はどこで確認できますか?
健康保険料率は協会けんぽや各健康保険組合、厚生年金保険は日本年金機構、雇用保険や労災保険は厚生労働省が毎年公表しています。また、国土交通省のガイドラインには参考となる「法定福利費率の考え方」も掲載されており、簡便算出時に役立ちます。
法定福利費の計算方法について、簡便法はどんなときに使えますか?
実務上、労務費に一律の率を掛ける簡便法は、見積作成の初期段階や概算段階で活用されることがあります。ただし、公共工事や正式な契約を伴う場合には、実際の料率に基づく正確な計算が原則です。特に説明責任が発生する場面では、具体的な根拠を示すことが不可欠です。
法定福利費に関するトラブルを避けるにはどうすれば良いですか?
最も多いトラブルは「法定福利費の過少・過大見積」と「根拠の不明確さ」です。適用除外者の扱いや、料率の適用範囲を明確にし、見積書の備考欄に根拠や出典を記載することで、受発注双方の誤解や後の交渉トラブルを回避することができます。
contact
あやなみ行政書士事務所への相談・お問合せは、以下の方法でご連絡ください。
*お問い合わせ内容により、有料相談になる場合がございます。(目安:5,500円税込/30分またはメール2往復程度)
*匿名及び非通知でのお問い合わせはご対応致しかねます。あらかじめご了承ください。
対応地域
神奈川県を中心とした首都圏に対応。
神奈川県:横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・保土ケ谷区・磯子区・金沢区・港北区・戸塚区・港南区・旭区・緑区・瀬谷区・栄区・泉区・青葉区・都筑区)|川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区)|相模原市(緑区・中央区・南区)|横須賀市|平塚市|鎌倉市|藤沢市|茅ヶ崎市|逗子市|三浦市|秦野市|厚木市|大和市|伊勢原市|海老名市|座間市|綾瀬市|葉山町
東京都:千代田区|中央区|港区|新宿区|文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区
千葉県:千葉市